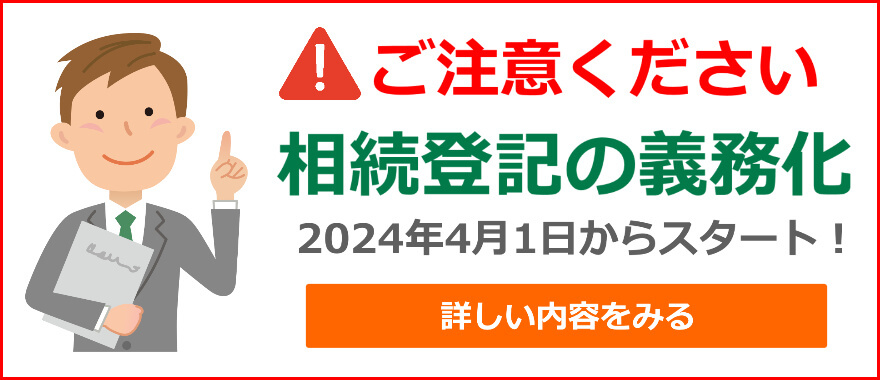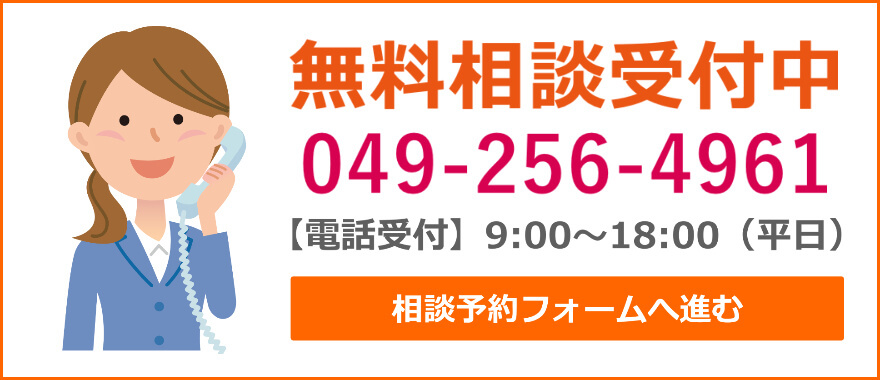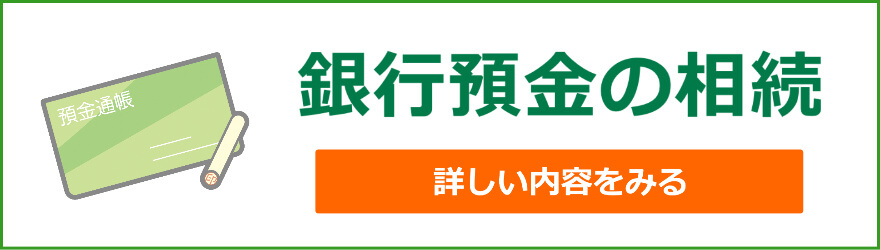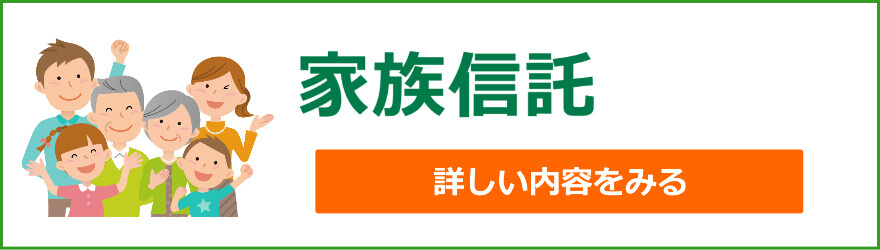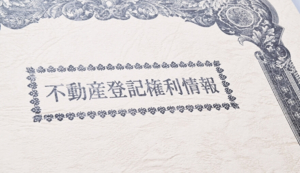相続登記はココから始める!不動産の調べ方・登記簿謄本の取り方を教えます!
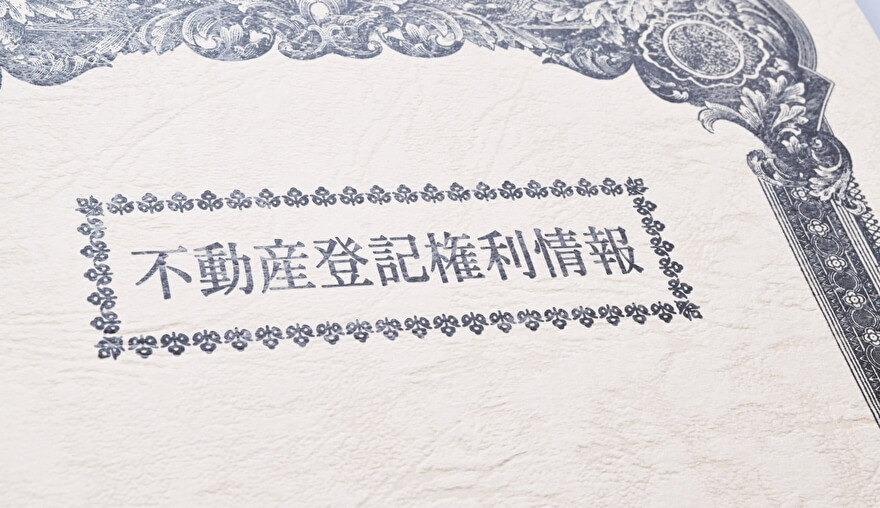
相続登記をするに当たって、まずはじめにすることは「不動産を確認すること」です。
親の名義だと思っていたら祖父の名義であったり、自宅だけだと思っていたら他にも不動産があったりと、相続では思わぬことがよくあります。
相続する不動産を確認するには「登記簿謄本」で行うことになりますが、今回は「登記簿謄本」を取得するまでをご説明します。
なお、「登記簿謄本」とは昔の呼び名で、現在は「登記事項証明書」といいます。しかしながら、一般的にはまだ「登記簿謄本」と言われることが多いのが実情です。
被相続人がどんな不動産を持っていたかを調べる

被相続人がどんな不動産を持っていたかを調べる場合、まずは「不動産の権利証」や「登記識別情報通知書」、「固定資産税の納税通知書」などを探してみます。
それらが見つかれば、その情報をもとに法務局で「登記簿謄本」を取得します。
もし、不動産の漏れが不安な場合は、市区町村役場で「名寄帳」を取得します。
名寄帳とは、ある人物がその市区町村で所有している不動産を一覧表にまとめたものです。
したがって、名寄帳を取得することによって、思わぬ不動産が見つかることもあります。
ただし、一覧表に記載されているのは、あくまでもその市区町村にある不動産だけで、他の管轄の不動産を調べることはできませんので、その点は注意が必要です。
名寄帳を取得するには?
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、請求者と被相続人との続柄が分かる戸籍謄本や身分証明書などが必要になります。
登記簿謄本を取得してみる!
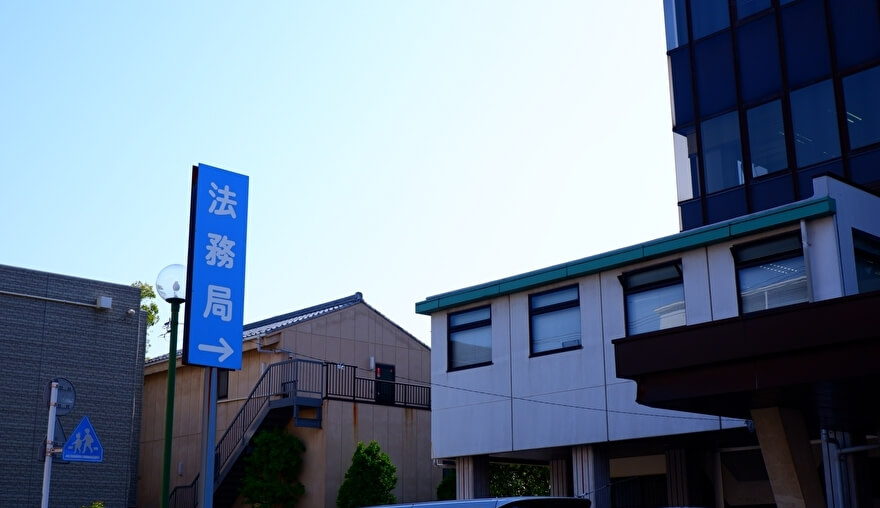
登記簿謄本は、どこの不動産であっても、全国のどこの法務局でも取得することができます。
また、不動産の所有者でなくても、誰でも取得することができます。
取得の際には、法務局の窓口に「登記事項証明書交付申請書」を提出します。
なお、登記簿謄本は、1通につき600円の手数料がかかります。
手数料は収入印紙で納めることになりますが、法務局には収入印紙売場がありますので、事前に収入印紙を用意しておく必要はありません。
住所と地番、家屋番号は違うことが多い!
これは、実際に登記簿謄本を取得するための申請書になります。

この申請書に必要事項を記入して請求することになりますが、注意しなければならないのは、不動産の「地番」や「家屋番号」を記載しなければならないことです。
「地番」や「家屋番号」は住所と異なることが多いので、その場合は住所をそのまま記載しても登記簿謄本を取ることができません。
「地番」や「家屋番号」は、「不動産の権利証」や「登記識別情報通知書」、「固定資産税の納税通知書」があれば、それで確認することができます。
もし、住所しかわからない場合は、不動産の管轄の法務局に問い合わせれば教えてもらえます。
このようにして登記簿謄本を取得して、不動産の所有者などを確認していきます。
まとめ
今回は、登記簿謄本で不動産を確認することについてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。
相続登記をする場合、不動産の所有者が両親か祖父母かによって、遺産分割協議書に押印してもらう相続人関係も変わってきてしまいます。
したがって、まずは不動産の権利関係を確認することが重要になります。